USDT(テザー)やUSDC、PayPayとの違いも解説
今日の日経電子版でも投稿されていた「金融庁承認」の公式ステーブルコインとなるJPYCについて、暗号資産なのか?暗号資産じゃないのか?という部分がモヤモヤしている人が多そうなので解説記事を書きます。
ちなみにJPYC側が「暗号資産ではない」と明言しているので、その根拠の部分をわかりやすく説明したいと思います。といっても僕も若干のモヤモヤは残りますがw
特急でまとめたので誤りやミスリードがあればすいません!
“発行・償還できる”機能が加わり国内初ステーブルコインに
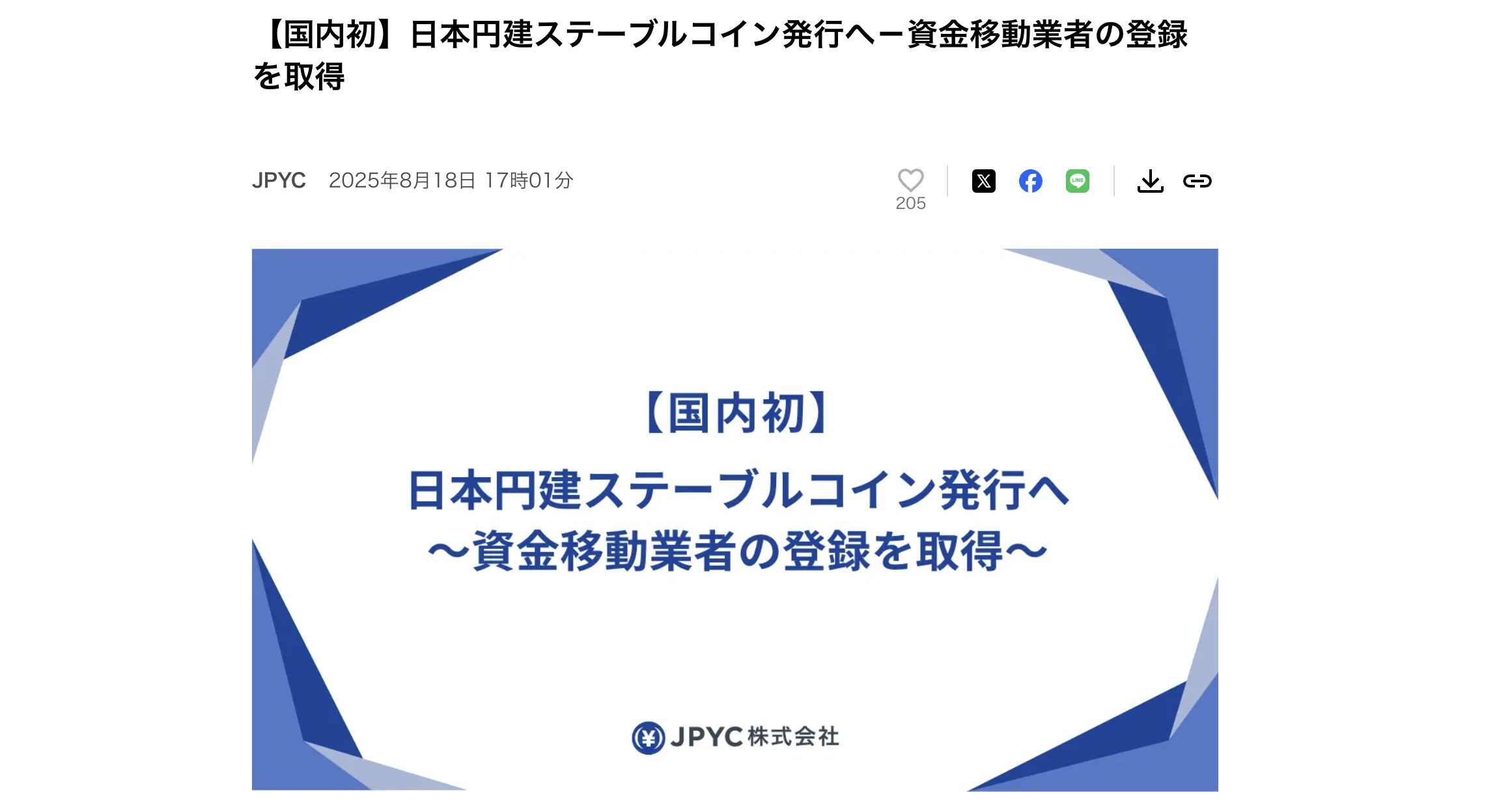
JPYC株式会社は2025年8月18日、資金決済法に基づく資金移動業者(関東財務局長 第00099号)として登録され、日本円と1:1で交換可能な電子決済手段(ステーブルコイン)「JPYC」を発行できる体制になりました。
プレスリリース:
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000054018.html
発行・償還は今秋に開始予定で、同社は新サービス「JPYC EX」として提供すると説明しています。新JPYCは円預貯金と国債で保全され、同額の円で償還できることがポイントです。
つまり、これまでのプリペイド型に加えて、1円で出し入れできる本格ステーブルコインになるということです!
ステーブルコインとは
ステーブルコインは、法定通貨などに価値連動させたデジタル通貨です。多くは発行残高相当の現金や短期国債で裏付け、1トークン=1通貨単位の信認を保ちます。日本では2023年施行の改正資金決済法で電子決済手段(デジタルマネー型ステーブルコイン)の制度が整備され、銀行または資金移動業者が発行・償還を担う枠組みになりました。
つまり、“値動きが安定するように設計されたデジタル通貨”で、日本では銀行や資金移動業者が出し入れを担うということです!
JPYCは現状“2本立て”(新:電子決済手段/旧:前払式)
新:JPYC(電子決済手段)は、1JPYC=1円で発行・償還でき、裏付け資産は円の預貯金と国債です。まずはEthereum/Avalanche/Polygonで発行予定です。暗号資産ではなく電子決済手段である点が公式にも明確化されています。
旧:JPYC Prepaid(前払式支払手段)は従来どおり存続しますが、制度上発行者による現金払い戻しは原則行いません。同社は「新JPYC(電子決済手段)」と「JPYC Prepaid(前払式)」を別トークンとして扱い、発行者による相互交換は受け付けないとしています。
つまり、“円に戻せる新JPYC”と“戻さないプリペイドの旧JPYC”が並走し、発行者の窓口で相互交換はできないということです!
新サービス「JPYC EX」:発行・償還をブロックチェーンで完結
同社は今秋、発行・償還(円⇄JPYC)をブロックチェーンで完結させる新サービス「JPYC EX」を開始予定とも発表しています。
当面の発行・償還・送金手数料は無料とされ、収益は裏付けの国債利息で賄うモデルを示しています。KYC/AMLはマイナンバーICチップ連携を使う方針で、ノンカストディ(利用者が自分のウォレット管理)、SDK無償公開によるプログラマブル送金も掲げています。さらに、発行・償還は1日100万円の上限がある一方で、利用者同士の送金や保有には上限がないと説明されています。
つまり、JPYC EXは“手数料ゼロで、口座→ウォレット→口座までをオンチェーンで素早く回す窓口”ということです!
価値の裏付けとビジネスモデル:円預貯金+国債で保全、利息で運営
新JPYCは、円の預貯金と(短期)国債で100%相当を保全し、1:1の償還を担保します。制度面でも要求払預貯金や国債等による保全・分別が重視されます。運営は国債の利息収入を柱とし、手数料無料をうたっています。
つまり、“現金と国債を裏に置き、利息で回すからユーザー手数料を抑えられる”ということです!
なぜ「暗号資産」ではないのか
多分多くの人がモヤっとしているポイント。JPYCは暗号資産ではありません!!!とJPYC社は言っていますが、ブロックチェーン上でありながら暗号資産ではないとは????ってなりますよね。僕もなりました。
簡潔にいうと新JPYCは日本の資金決済法上の電子決済手段であり、法定通貨(円)と価値連動・1:1償還が可能です。価格変動を前提とし償還保証がない暗号資産とは制度も性質も異なると、同社は公式に明言しています。
つまり、常に1円で出し入れできるよう制度設計されたデジタル円で、投機的な暗号資産とは別物”ということです!
ちなみにこの点でいうと日本の資金決済法上はUSDTもUSDCも暗号資産ではないです。
たぶん僕らのモヤっとは
①ブロックチェーン上にあるトークン=暗号資産
②すでにグローバルに確立しているUSDT、USDCの2大ステーブルコインが他のクリプトと一元的に「暗号資産」括られている感覚からステーブルコイン=暗号資産
というバイアスにあるのだと思います。あくまでも「日本の法律上」は暗号資産ではないということです。
USDT/USDCとの違い(要点まとめ)
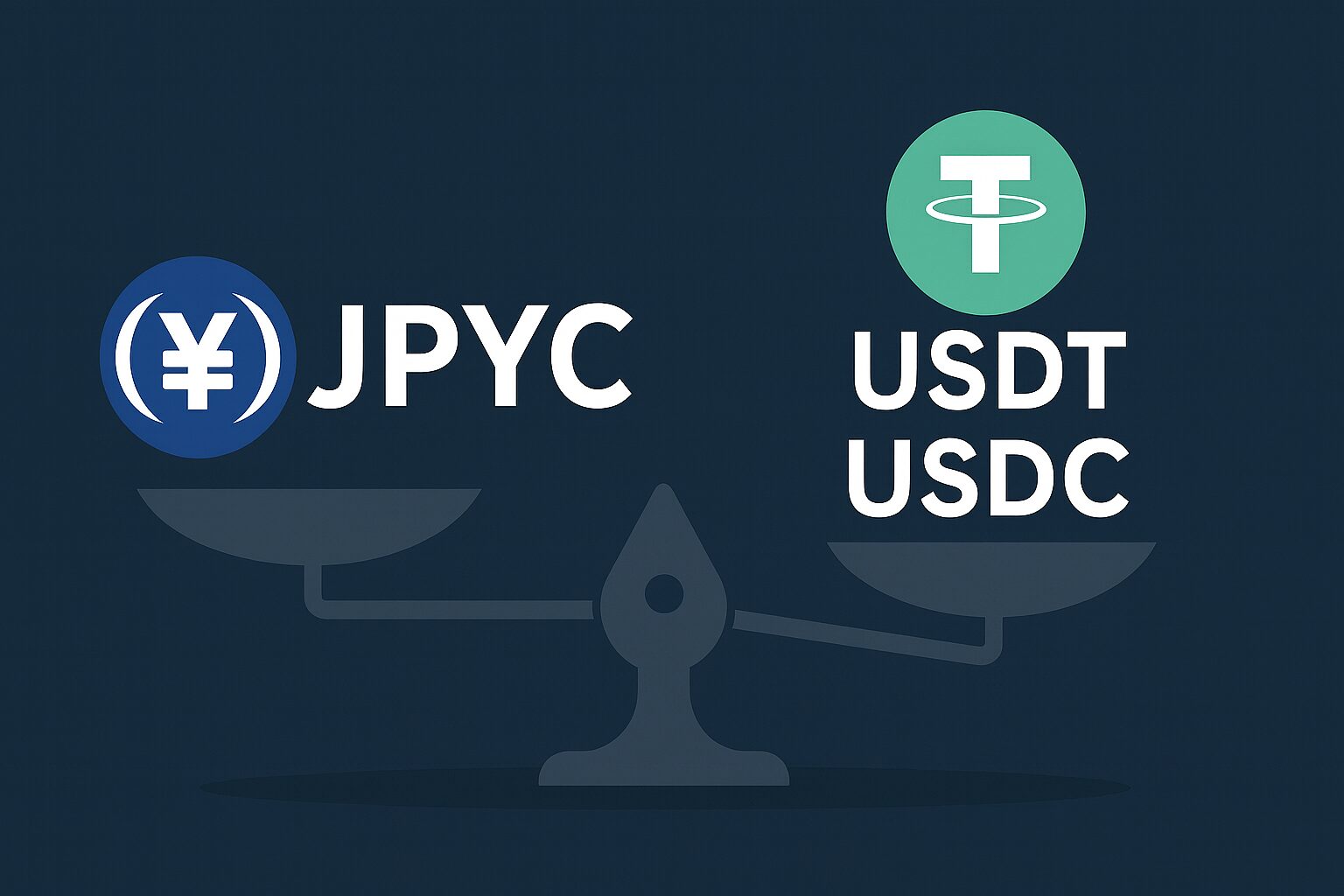
- 通貨建て:JPYCは円、USDT/USDCは米ドル
- 発行体・規制:JPYCは日本法に基づく資金移動業者(JPYC社)が発行・償還し、円実務(会計・税務)に親和的です。USDT/USDCは海外発行体のドル建てで、グローバルDeFiで流通
- 償還:JPYCは1:1で円償還。USDCは1:1でUSD償還を前面、USDTも条件付きで対応します。国内での円ダイレクト償還は、国外ドル建てステーブルでは原則想定されません
つまり“JPYCは円に最適化された国内制度準拠、USDT/USDCはドル基軸の世界汎用”ということです!
電子マネー(PayPay等)との違い

このPayPayとの違いや優位性についてはSNSでもかなり考察?を見かけるので簡単にまとめます。超ざっくりいうと
JPYC=“オープンなオンチェーン最終決済+利息収益でユーザー手数料ゼロ”
PayPay=“閉域PSP型でネットワーク運営・加盟店向け価値提供を手数料で回収”
という構図なので、そもそも事業としての収益構造が異なります。JPYCが店舗等に決済手段として導入されると、店舗や小売業者からすると手数料が全然取られないのにキャッシュレス導入できるのでめっちゃハッピー!という感じ。
僕らユーザー側は強いて言えばPayPayみたいな強めのキャッシュバックやポイント還元はJPYCには期待できなそう。という感じ(これは実際わからない)。
なぜPayPayと比較されるのか
なぜJPYCはPayPayより安いと比較されるのかもう少し深掘ります。混乱しないように、あくまでも決済手段としてJPYCを導入する事業者側の目線です。
ネットワーク構造の差
JPYCはパブリックチェーン上の即時・最終決済で中間事業者が少なく、ネットワーク料や清算コストの多段手数料がほぼ発生しません。PayPayはPSP型の多層ネットワーク(加盟店管理・清算・不正対策など)で、加盟店手数料1.6%前後が基本設計です。
収益源の差
JPYC(電子決済手段型)は裏付け資産(預金・国債)の利息を主な収益にできるため、発行・償還・送金を当面ゼロ手数料にできます。PayPayは手数料収入が中核です。
リスク設計の差
JPYCはオンチェーン移転=原則最終でチャージバック前提ではないため、未回収や不払リスクに備えるコストが小さくなります。PayPayは不正・返金対応コストを見込みます。
運用コストの差
JPYCはSDK/スマコンで請求・消込・分配を自動化しやすく、運用費が下がります。PayPayは加盟店サポート/端末/審査などオフチェーン運用の固定費が大きめです。
ただしJPYC側にも実費はあります
ガス代(チェーン手数料)、銀行振込手数料、ウォレット管理コスト、(使う場合は)ゲートウェイの小口料。
発行・償還は1人1日100万円上限など運用上の制約も考慮が必要なので、実際にJPYCが爆発的に普及するかはこの辺の事業者にとってのメリデメの部分が大きく左右するんじゃないかな〜と思います。
使い道:消費・B2B・Web3・公共まで
じゃあJPYCはどういう使い道があるのか?ざっくり想定されるケースをまとめてみました。
ユーザー(消費者側)
ECやデジタル課金を円建てで即時決済、P2P送金も数分で完了します。
Web3(NFT/ゲーム/DeFi)でも円建てで使える。
事業者側
決済手段の多様化、B2B送金の即時化/国際送金の低コスト化、スマコンによる自動分配などもできるようになると思います。おちんぎんがJPYC!?なんてこともありえる。現に給料PayPayもありますし・・
つまり“日常決済から企業間決済、Web3までを横断する“円のデジタル基盤””になりえるということです!
新旧JPYC早見表(要点比較)
そろそろ混乱してきたと思うので、ここで一旦新旧のJPYCで何が違うのかまとめてみました。
| 項目 | JPYC(新・電子決済手段) | JPYC Prepaid(前払式) |
|---|---|---|
| 法的位置付け | 電子決済手段(資金決済法) | 前払式支払手段 |
| 裏付け | 円預貯金・国債で保全 | 前払金相当の管理(原則払戻し不可) |
| 発行/償還 | 1:1で円と交換(JPYC EX) | なし(原則) |
| 手数料 | 当面無料(発行・償還・送金) | 取引先サービスに依存 |
| チェーン | Ethereum/Avalanche/Polygon | 複数チェーンで流通(従来どおり) |
| 交換可否 | 発行者窓口で円⇄JPYC | 発行者による新旧相互交換なし |
つまり、新JPYCは出し入れ自由なデジタル円、旧Prepaid型JPYCは使って消化するプリペイドということです。
まとめ:JPYCは“本格的に使える円のデジタル基盤”となるか
JPYCは前払式(戻さない)に電子決済手段(1:1で戻す)が加わり、実務で“出し入れ可能なデジタル円”を提供するフェーズに入りました。JPYC EXで発行・償還・送金がオンチェーンで回り、手数料ゼロ方針と国債利息モデルにより、日常決済からB2B・国際送金・Web3までの広範なユースケースが射程に入ります。
制度・仲介・UXの整備が進めば、円建てステーブルコインの本格普及が現実味を帯びます。僕らが毎日コンビニやスーパーでPayPay♪ってやってる感じでJPYC⤴︎♪みたいな決済が当たり前にやってる光景になるかもしれないと思うと僕らクリプト民としてはちょっとワクワクするよね。
仮想通貨じゃないですが!!!笑
(日本法上)
というわけでJPYCについて現時点でわかっていることをまとめてみました。
ステーブルコインは世界的なムーブメントで莫大な資金が集まっている特大トレンドなので、今後も追っていこうと思います。















